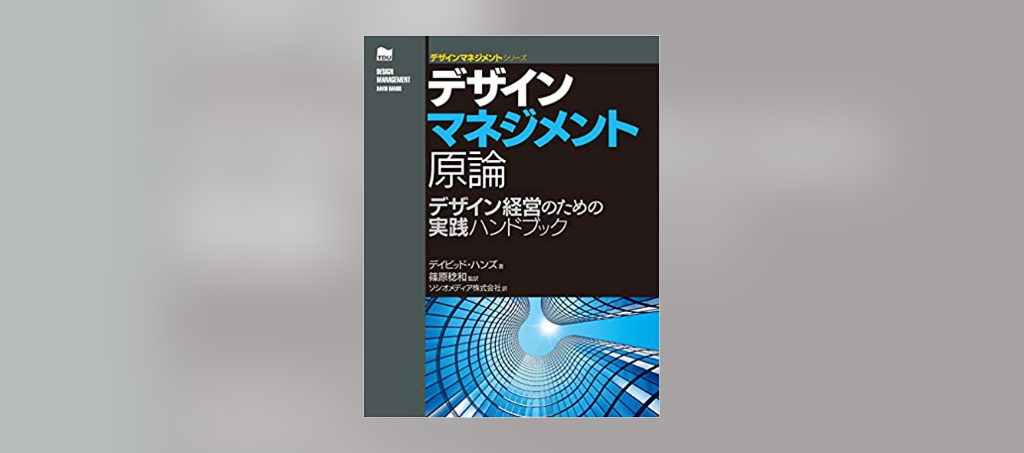
- この本について
- 第一章 デザインの価値
- 復習の問い
- Q1. デザインは組織に様々な価値をもたらす。デザインを通じてどこで価値が創造されるかを、正確に述べることができるか。
- Q2. 組織、とりわけ中小企業にとって、デザインを導入する上での主な障害は何か。
- Q3. デザインに対して賢明なアプローチをとっている著名な組織の例を示せるか。それらの組織は、どこでどのようにデザインを高度なレベルで活用しているか。
- Q4. 民間セクターと異なり、利益を主な優先課題としない公共セクターの組織では、デザインがどのように価値をもたらせるか。
- Q5. Nosibooの事例において、デザインがどのように国際市場での地位の強化に役立ったか。
- Q6. 組織がデザインラダーを上がっていこうとする際に、短期的及び中期的に直面する課題にはどのようなものがあるか。
- Q7. 事業計画を策定する活動において、どこでどのようにDMIデザインバリュー・スコアカードを使うことができるか。
- Q8. イギリスのデザインカウンシルは、デザインプロセスのモデルとしてダブルダイヤモンドを開発した。その4つのステージは何か。
- 復習の問い
- 終わりに
この本について
前書きを一部抜粋する。
本書の使い方
本書は、デザインマネジメントという専門領域に直接的または間接的に結び付けられる重要なテーマを中心に構成されている。この専門領域には、学問領域と実践領域の両方が含まれ、これらは互いに影響し合っている。読者の希望次第で、各章をバラバラに読むこともできれば、全編を通じて読むこともできる。
〜
各章の学習要素は、以下のように構成されている。
- 分かりやすく明確に構成した文章。これには「この章の狙い」と「まとめ」が含まれる。
- 主なポイント: 読者の参考となる一連の論点を示している。
- チェックリスト: その章で取り上げた主なポイントを簡潔な箇条書きにまとめている。
- 復習の問い: その章の考察内容について振り返り、どのようなことを観察し、どのような洞察を得たか考えるように促す。ここで問われる質問を通じて、その章のポイントやテーマをおさらいし、簡潔かつ全体的な理解を確立していく。
- プロジェクト用の課題: 多くは復習の問いに密接に関連していて、論点やテーマを教室でのプロジェクトに発展させるよう促す内容となっている。プロジェクト用の課題は、デザインマネジメントやデザインとイノベーションといった講座やコースで学生(特に大学院生)が取り組む典型的な研究プロジェクトといえる。論点を議論したりデザインマネジメントの理論と実践を深く研究したりするよう奨励する課題で、学生や実践者が個人または少人数のグループで取り組むセミナー活動の基礎として使うこともできる。
- 参考文献・推薦文献: その章の主なテーマに言及している、あるいはそれを議論している補足的な著作物や学術論文などを提示する。
- ウェブリソース: その章のトピックを補完する情報とリソース。現時点でオンラインで広く無料公開されているリソースを慎重に選んでいる。
- 用語解説: 本書の末尾で各章のキーワードを説明する
読み流すだけではもったいなく、せっかくならこの掲示された形式に則り各章の「復習の問い」に対し自分なりの解釈を残し学びへと昇華したい、と思って、試しに書いてみた。
第一章 デザインの価値
復習の問い
Q1. デザインは組織に様々な価値をもたらす。デザインを通じてどこで価値が創造されるかを、正確に述べることができるか。
商業市場の競争激化や新しい技術の登場などにより、事業モデルの確立と破壊が繰り返されている現代。不確実性の多い状況下で、消費者のニーズの素早い変化にも順応し、組織(供給)と市場(需要)を結びつけ、顧客が求めている以上の革新的な体験を創造し、長期的で持続可能な成功を手に入れるためにもデザインは不可欠な要素となっている。顧客のニーズを満たすクリエイティブな提案、「製品」への価値付与・改善も「デザインの実践」ではあるが、ごく一部である。そうしたデザインの実践を包括的に捉え、現代に適した競争力ある事業提案を実現することがデザインマネジメントだ。
デザインのわかりやすい価値は、目に見えない価値を有形化し、社内外の幅広い関係者や顧客にも見てわかる状態にすること。有形化の例としては、建築環境、デジタルアプリケーション、グラフィック、販促物、デジタルデバイス、付属のパッケージなど。同時に、組織の戦略やサービスのポリシー・プロセスといった無形の価値を示し伝えることもできる。つまり、消費者やエンドユーザーに歓迎される幅広い価値提案の実現(創造)が可能である。
Q2. 組織、とりわけ中小企業にとって、デザインを導入する上での主な障害は何か。
その組織に組織拡大する能力がなく、そもそもその欲求も少ないこと。また、デザインに対して無理解であり、どんな価値をもたらされるか知らないこと。
Q3. デザインに対して賢明なアプローチをとっている著名な組織の例を示せるか。それらの組織は、どこでどのようにデザインを高度なレベルで活用しているか。
- Boeing: 産業製品
- Samsung、Apple: テクノロジー
- Nikon、Bosch: 消費者製品
- L'Oréal、Estée Lauder: 化粧品
- Hawes & Curtis、Juicy Couture: アパレル
- Emirates、Lufthansa: 航空
- Missguided、Boohoo: オンライン小売
- Waitrose、Booths: 小売
競合他社より魅力的なサービスや製品を作ることで、根本的には同じ製品に対して高い価格を付与することができている。
Q4. 民間セクターと異なり、利益を主な優先課題としない公共セクターの組織では、デザインがどのように価値をもたらせるか。
この「公共セクター」とは医療機関、交通機関、教育機関などを含む。利益に直結せずとも、有意義で質の高い「環境」「システム」「体験」「ルール(制度)」を創造することで、利用者により大きな価値を提供し、そうした機関のイメージや有効性を向上できる。
Q5. Nosibooの事例において、デザインがどのように国際市場での地位の強化に役立ったか。
Nosibooを開発したAttract Ltd.は、もともとインテリアデザインと製品開発を中心とした会社だったが、2011年に「革新的でコンテンポラリー(時代の特色を活かした)デザインの要素があり、輸出の潜在性が高い製品」の開発を目指し新しい取り組みを始めた。その製品コンセプトは「革新性があり、子供に優しく、ポジティブなメッセージを発するベビー用品」とし、中長期的な目標として「自国(ハンガリー)内で開発・製造した製品による国際的なブランドの構築」を掲げた。
2年の様々な取り組みを経て製品化し、2013年秋に販売された。2014年には国際的なデザイン賞「Red Dot Design Award」の医療機器部門を受賞。ハンガリー国内におけるベビー用品店・ドラッグストアの流通販売網をほぼ網羅し、販売国もヨーロッパの8国にわたっている。さらに新しい製品の開発にも邁進している。
Q6. 組織がデザインラダーを上がっていこうとする際に、短期的及び中期的に直面する課題にはどのようなものがあるか。
デンマークのデザインラダーは、組織にデザインを取り入れる4つのステージを示している。
デザインラダー 4段階のデザイン成熟度
— ろくぜうどん (@rokuzeudon) 2020年1月23日
1.デザインの活用なし
2.スタイルとしてのデザイン
3.プロセスとしてのデザイン
4.戦略としてのデザイン
中期的には、そもそも戦略レベルで「デザイン」を活用しようという経営レベルでの合意があるかどうか。得るためには、「デザインがどのような価値をもたらせるか」を目に見える形や指標にして示し、議論などのデザインコミュニケーションを繰り返していく必要がある。
短期的(各ステージ)においては、次のステージに進むための取り組みを誰がどのように推進するのかが課題になるのではないか。ステージが上がるにつれて、関係者もデザインの対象となる領域も増えていく。各分野に精通した人材をどう確保または育成し、そしてどのように合意形成しデザインを戦略的に推進するのか。
Q7. 事業計画を策定する活動において、どこでどのようにDMIデザインバリュー・スコアカードを使うことができるか。
DMIデザインバリュー・スコアカード(手法)の実践は次の3つの手順となっている。これによって、組織におけるデザイン測定法と投資の枠組みを策定し、戦略的なデザインマネジメント策定の材料にできる(らしい)。
企業の組織内のデザイン評価 3つのプロセス(DMI)
— ろくぜうどん (@rokuzeudon) 2020年1月23日
1.組織内のデザイン価値の評価と測定
2.デザインの役割とデザインバリュー・スコアカード
3.デザイン投資と将来の成長
あまりピンとこなかったので公式サイトも見てみた。
https://www.dmi.org/page/DesignValuewww.dmi.org
肝心の資料がリンク切れだったがググったらでてきた。
気力さえあれば別途翻訳して記事にしたい…。
Q8. イギリスのデザインカウンシルは、デザインプロセスのモデルとしてダブルダイヤモンドを開発した。その4つのステージは何か。
- 発見
- 定義
- 開発
- 提供
なお、こちらの記事が簡潔にまとめられている。
終わりに
「デザイン」が組織の戦略や経営に密接に関係していて、役に立つものだという趣旨が簡潔にまとめられていて良かった。また、「効果的でアジャイルなデザインプロセスのシステム」についてこの本でも少し登場したのが意外だし安心した。
本の構成に沿って今回のように読み進めていると時間がかかりすぎるので、次は興味のある章毎にさっと読み進めてみたい。
いろいろ新しいキーワードが得られ、じっくり調べたり関係する企業に話を聞いてみたい箇所も多いのだが、時間のある学生時代にこういうことをじっくり学んでおけば良かったな〜としみじみ思うなど。まあ社会人になって組織の活動とか経済活動に興味や理解がある今だからこそそう思うのだろうけど…。
